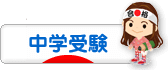ボリュームゾーンにおける、過去問の相性
次女の6年生を通じた偏差値は58でしたが、理系と文系で随分と教科間格差があるタイプでしたので、かなりクセ強の偏差値58でございました。
比較的算数は得意だったのですが、とあるラインに壁があり、例えば偏差値66の市川の算数は4割とか5割しか取れないのに、偏差値63の東邦大東邦は8割とか9割を取れるという、そういった傾向もありました。
では、東邦大東邦は8割も9割も算数で取れるのだから楽勝だろうかと言うとそういうことではありません。
不得意科目の社会が足を引っ張る上、記号問題しかない東邦大東邦の国語は『むしろ真の国語力がないと解けない』ということもあり、前期は1勝もできず、むしろ倍率や偏差値が高いはずの後期の方が勝てたりと、すっちゃかめっちゃかだったりするわけであります。
私の入試に対する考え方というのは、偏差値60くらいまではまさに「偏差値通り」。
奇をてらった問題が出るわけでもありませんから、対策もなにも偏差値がそのまま合否につながるだろと、そんな感覚を抱いていたわけでありますが、いざ娘が過去問を解き始めてみると、ぜんぜん全く違う。
同じような問題に見えても、配点やそれぞれの教科の平均点、教科の傾向などによって相性が存在するものであり、ダメなところはダメ、イケるところはイケる。意外とハッキリしたモノがありました。
さて、そうなると他に相性が良い・対策が間に合いそうなところはないかと慌てて探したりするわけですが、これが一目瞭然と申しましょうか、すぐに見つかったりはするもので、我が家では意外なところに2校、「これは確実に取れるぞ!」という学校がありました。
1つは算数の配点が少し他よりも高く、1つは算国理社すべての方向性が娘が対応できる傾向と丸かぶりと、よく見ればその相性にはしっかりとした理由もありました。
ところが、そもそもこの発見自体が遅れています。
元々予定していたわけでもないこの2校は、今から候補にできうるのか?という段階だったりもしました。
慌てて1校は1月に最後に説明会がありましたので訪れたりするのですが、1校はそういったものには間に合わず、この発見の遅れは大きな痛手となりました。
恐らくもう少し早くからわかっていれば、かなり戦略は変わっていたような気も致します。
過去問というのは「あまり早く始めるな」と言われることがあります。
確かに早く始めても点数が届くわけがありませんし、まだまだ未熟なうちから解いても焦りがつのるばかりで、それは非常によく理解できる話であります。
ただ、私としては、それこそ1教科ずつ、少しずつでも良いので、得点はひとまず置いて、相性を見るような、そんな視点で早くからトライしてみる、なんなら親だけは見ておくというのは、すこぶるアリなんではないかとも思ったりします。
志望校というのは、まず自分が行きたいところ、熱望するところに自らも合わせていく。そういった姿勢が必要なのは、それは当然として、
併願校については、自分が行けるところ、対策がしやすいところ、相性が合うところから探してみる。これもひとつの縁であると考えます。
我が子は教科間格差という問題を抱えていたゆえの話なのかもしれませんが、必ず意外な発見があると思います。
 |
| きっと3校はこ゚縁がある学校があるッ!? |